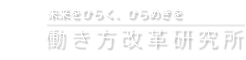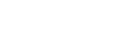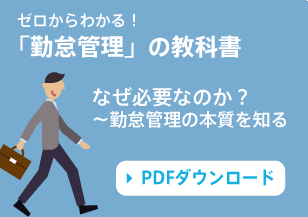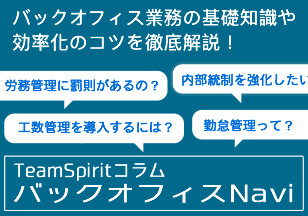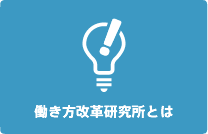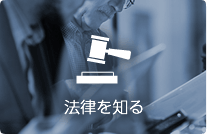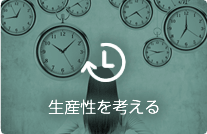働き方の多様化が進む現代では、企業に属する従業員の立場や属性もさまざまです。正規雇用が大半だった時代は終わり、パートタイムや有期雇用、派遣など雇用形態も多岐にわたります。もちろん、それぞれのワークスタイルに合わせて雇用形態を選択できているという意味では、多様化が進んでいると言えるでしょう。しかし、「正社員との待遇格差」が広がっているという根深い問題が存在します。
特に注視すべきは、同じ業務内容でも雇用形態の違いで給与額が異なる点です。それは従業員の成果や能力ではなく、雇用形態で待遇が決まる状況になっていることを意味します。そうした状況を是正するために2020年4月から(中小企業は2021年4月1日から)大企業に適用されたのが「同一労働・同一賃金制度」です。企業としては、待遇格差についての損害賠償請求トラブルを避けるためにも、同一労働同一賃金制度への対応が不可欠となります。
不合理な待遇格差を埋める「同一労働同一賃金」とは
同一労働同一賃金とは、同じ企業や団体で働く従業員間において、不合理な待遇格差を解消することを目的に生まれた制度の1つです。現代の日本社会では、雇用形態による待遇格差が拡大傾向にあります。そのため、正規雇用および非正規雇用にかかわらず、同程度の業務・責任を担う労働に対しては、基本給や賞与、その他手当や福利厚生においても同じ条件にする仕組み作りを目指しています。
同一労働同一賃金は「パートタイム・有期雇用労働法」(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)で規定されており、大企業は2020年4月1日から開始。その他の中小企業においても2021年4月1日から適用されることが決まっています。そのため、経営者は十分に法律を理解したうえで対策を講じる必要があり、そうでなければ従業員との間でトラブルに発展するリスクがあると言えるでしょう。

法律によって明文化されたことによって、従業員側からの申し入れや交渉は以前よりも進めやすくなるでしょう。しかし、現状では違反した場合でも罰則規定はありません。罰則がないからと言って法令違反してしまうと、企業としての信頼を失うだけではなく、従業員の人材流出などにもつながりかねないでしょう。法令遵守を果たし、同一労働同一賃金の体制を構築することは企業としての責務と言えるのです。
同一労働同一賃金制度において企業に求められること
同一労働同一賃金体制の構築のために企業がまず取り組むべきことは、自社で働く従業員の待遇の状況把握です。自社の正規雇用・非正規雇用の割合がどれくらいで、それぞれの給与形態や賞与、その他手当にどのような違いがあるのかを明確にしましょう。同一労働同一賃金の実現にあたっては、正規雇用と非正規雇用の間にある不合理な待遇格差をなくすことが大前提です。そして、もし何らかの理由によって待遇差が生じてしまう場合は、企業にはどんな差があるのかを明確に説明する責任があります。
不合理な待遇差とは?
もし正当かつ明確な理由がないまま待遇差を設けている場合は、法令違反とみなされる恐れがあるため、早急に人事制度の改正や給与形態の見直しを図る必要があります。しかし、そもそも不合理な待遇差の実態をきちんと認識しなければ、制度の是正は実現できないでしょう。
端的に言えば、「パート、または派遣だから」「将来の役割期待が異なるため」という主観的・抽象的理由で、待遇差が生じることこそが不合理な待遇差と言えます。たとえば、正社員と非正規の従業員が同じ業務内容の仕事をしているにもかかわらず、立場の違いだけを理由に待遇差が生じることはフェアではありません。企業への利益貢献度や業務に対する責任の度合いを踏まえるのであれば、立場は異なれども同じ待遇にすべきなのは当然のことだと言えるでしょう。
不合理な待遇差のユースケース
従業員の待遇に関する代表的な項目としては、「基本給」「賞与(ボーナス)」「通勤手当」「福利厚生」が挙げられます。どのような場合に不合理な待遇差が生じるのか、もしくは合理的な判断なのかを、項目ごとに紹介します。ユースケースを参考に自社の現状を一度、見つめ直してみましょう。
1.基本給
| 能力・経験について問題とならない例 | 能力・経験について問題となる例 |
|---|---|
|
|
| 業績・成果について問題とならない例 | 能力・経験について問題となる例 |
|---|---|
|
|
| 勤続年数について問題とならない例 | 勤続年数について問題となる例 |
|---|---|
|
|
2.賞与(ボーナス)
| 問題とならない例 | 問題となる例 |
|---|---|
|
|
3.通勤手当
| 問題とならない例 |
|---|
|
4.福利厚生
| 問題とならない例 |
|---|
|
法内容に沿っていなければ社内制度の見直しが必要
同一労働同一賃金を実現するためにも、まずは自社の状況が法内容に沿っているか社内制度を点検しましょう。正社員と非正規の従業員との間で不合理な待遇差が生じている場合は、賃金形態や就業規則の変更も視野に入れた抜本的な改革が必要となります。ただし、ユースケースの事例で紹介した通り、一概に待遇を同じにすれば良いというものでもありません。職務の内容や求められる役割、責任など、従業員の労働環境を考慮しながら総合的に判断する必要があります。

仮に正社員とパートタイムの従業員の賃金形態をまったく同じ状態にすると、今度は責任の度合いが大きい仕事に従事している正社員に対して不合理になってしまうことも考えられます。また、「同一労働同一賃金」という名称だけに基本給や賞与のみに着目してしまいがちですが、実は通勤手当や福利厚生などにおいて格差が生じているケースもあるため、細部にわたり注意する必要があるでしょう。
手順を踏まえて同一労働同一賃金への取り組みを
企業が同一労働同一賃金に対応するためには、現状を把握したうえで適切な手順を踏んで準備することが重要です。厚生労働省が紹介している手順をもとに、企業が取り組むべき具体的な対策をチェックしましょう。手順通りに行うことで同一労働同一賃金に関する社内での取り組みがだいぶクリアになるはずです。
| 手順1.労働者の雇用形態を確認 |
|---|
| 「パートタイム・有期雇用労働法」の対象となる従業員がいるかをチェックします。具体的には「パートタイムの従業員」「有期雇用の従業員」「派遣社員」が対象になります。 |
▼
| 手順2.待遇状況をリストアップ |
|---|
| 基本給、賞与、通勤手当、福利厚生のそれぞれの項目について、正社員と非正規雇用のスタッフ間でどんな違いがあるのかをリストアップします。 |
▼
| 手順3.待遇差の理由を精査 |
|---|
| 正社員と非正規雇用のスタッフ間で待遇差がある場合、なぜそうした差が設けられているのか確認します。人事制度を制定した当時と比べ、状況が変わっていることも考えられます。その待遇差が明確な根拠に基づき「不合理ではない」と証明できるか否かをきちんと精査しましょう。 |
▼
| 手順4.待遇差が不合理ではないことの証明 |
|---|
| 待遇差の理由について確認した結果、明確な根拠や理由があって「不合理ではない」と判断した場合、それを証明するための資料や説明する内容を整理します。従業員に説明を求められた場合に明確に回答できるよう、文書にまとめておくのがベストです。 「パートタイム・有期雇用労働法」においては、従業員から待遇差の説明を求められた場合、企業にはそれに応じる義務が生じることが明記されています。法律面から考えても重要事項となるため、第三者が見た場合でも納得できる内容を整理しておきましょう。 |
▼
| 手順5.改善すべき項目の整理 |
|---|
| 「不合理な待遇差ではない」と証明できない場合、企業としては改善に取り組む必要があります。問題点を整理したうえで、どの部分の改善が必要なのかを1つずつピックアップしていきます。 |
▼
| 手順6.改善計画の立案と実行 |
|---|
| 改善すべき項目が決まったら、いつまでに完了させるのかも含めて計画を立案します。たとえば、基本給や賞与支給のルールを見直さなければならない場合、就業規則の変更が必要になるでしょう。また、従業員の意見を参考にしなければならないケースも多いため、計画的に取り組む必要があります。 |
雇用形態にとらわれない能力重視の正しい賃金制度に
同一労働同一賃金は従業員にこそメリットがあり、企業側にとっては人件費の面でデメリットが大きいものと考えられがちです。しかし、公平な人事評価が定着すれば、雇用形態にかかわらず優秀な人材が集まりやすくなるという利点があります。能力やスキルがあり、高い成果を見込める人材にとっては魅力的な賃金制度であり、それが他の従業員にとってもモチベーションにつながっていくはずです。
長らく日本では年功序列型・終身雇用型の人事制度が定着してきた歴史があります。安定的な雇用を生み出す意味ではメリットも大きい仕組みと言えました。しかし、一方で高い成果を出し続けてきた優秀な人材にとっては、やりがいを感じにくい制度であったことも確かです。
同一労働同一賃金は、旧来型の人事制度を根本から見直しを図る、本質的な働き方改革の一環とも言えます。こうした動きは大企業・中小企業を問わず、今後もますます加速することが考えられます。公平な人事評価を行っている企業であると信頼され、優秀な従業員を確保するためにも、企業は一刻も早く雇用形態にとらわれない能力重視の賃金制度に切り替えていく必要があるのではないでしょうか。
text:働き方改革研究所 編集部