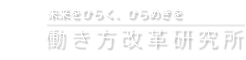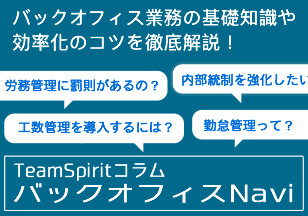日本たばこ産業(JT)といえば、言わずと知れた「たばこ事業」を中核とする企業だ。一方で、医薬や加工食品事業も展開するように、そのビジネス領域は幅広い。そんなJTは、従業員の多様化や女性活躍の推進を率先して取り組む企業でもある。 JTが多様化や女性活躍の推進に取り組むようになったのはなぜだろうか。そして現在までにどのような考え方によって、どのような施策を展開してきているのだろうか。JTで、その名もズバリ「多様化推進室」の室長を務める金山和香氏に、JT流の多様化の姿を尋ねた。

JTは1985年に旧・日本専売公社から業務を継承した株式会社。国内でのたばこ製造・販売はもちろん、世界120以上の国と地域でたばこを販売する。さらに医薬品の研究開発やグループ会社を通じた加工食品事業も手がけている。イメージとしては、「昔からある大企業」に近いところだろう。しかし、そんなJTは多様化(ダイバーシティ)の推進に積極的に取り組む企業という一面も持つ。2016年には、「新・ダイバーシティ経営企業100選」や「なでしこ銘柄(女性活躍推進に優れた上場企業)」に選定されたほか、「PRIDE指標(LGBTに関する取り組みの評価指標)」で最高評価のゴールドを獲得。多様化推進の先進企業なのだ。
JTの多様化推進室で室長を務める金山和香氏は、多様化推進の背景について、こう語る。
「1999年に米RJRナビスコから米国外のたばこ事業を取得し、JTインターナショナル(JTI)を設立したことが1つのきっかけになっています。それまでは主に日本国内で事業をしてきましたが、国外の市場も開けたわけです。それも、どこか1国ではなく、グローバルの多数のマーケットが対象です。当然のことながら、いろいろな人が働いているので多様性を意識しますし、国の違いや企業文化の違いを考えながら働かざるを得なくなりました」
とはいえ、国内のJTにはすぐにその風は吹いてこない。2012年に代表取締役社長に就任した小泉光臣氏は、たばこのマーケットやビジネス環境、イノベーションに変化の起こる度合いが大きくなると見越し、多様化をその原動力として生かすことを推進する方針に打って出たのだという。海外のモノの生み出し方や仕事の仕方を、会社全体としても受け入れていこうという考えだ。
「しかし、多様化、ダイバーシティを生かしていくと言っても、日本国内のJTを見ると、そこは"日本人・中年・男性"が大多数を占めるモノカルチャーな世界でした。マイノリティーの中ではマジョリティーである女性ですら、活躍できていない状況だったのです。そこで、多様化の推進を女性の活躍から広げていくことを経営課題として取り組むことになりました。2013年のことでした」
そして、多様化の推進をミッションとする多様化推進室が同年設立された。当時は金山氏ともう1人の若手男性社員の2人がメンバーで、JTの多様化への取り組みが始まった。
現場の経験を通じて「生きた多様化」を推進
ダイバーシティ推進というと、人事部門の役割というイメージが強い。JTでも多様化推進室は人事部門の1つではある。しかし、2016年11月時点で男性3人、女性5人の8人で構成する多様化推進室には人事出身のメンバーはいないという。多様化推進室を任せられた金山氏自身が、そもそも同社の製造工場出身なのだ。
「多様化を推進するメンバーには、まず経験として多様なものを持っていることが必要だと感じています。現場の経験や肌感というのでしょうか、会社を良くしていこうと考えるときはどのような施策をどのような目的で行っていけば受け入れられるかを考えながら進めなければなりません」
多様化の推進とはいっても、いきなり人員構成を変えて女性や外国人を増やすというわけではない。まずは考え方や仕事の仕方、働き方に「違うものがあってもいいということを受容してもらう」(金山氏)ことこそが、多様化推進の第一歩であるとし、そうした中で、多様化推進のカギを握るのは、管理職だったと金山氏は振り返る。
「管理職の中には変わることに躊躇する傾向がある人もいます。成功体験を重ねて管理職になった人の多くは、仕事の仕方に自信があります。そして部下にも成功してほしいとの思いから、自分の成功体験を教えていくわけです。しかしそれだと、どうしても従来の方法や考え方にシフトしていってしまうのです。そこで、多様化推進室は、まず管理職の考え方を変えていくようなアプローチを取りました。違う考え方をどのように受容していくか、受容していく姿をどのように他の人に見せていくかがポイントでした」
管理職へのアプローチは徹底したという。2014年、当時約1300人の全管理職を対象とした研修を開催したのだ。なぜ多様化を進めていくのか、そして自分の組織でダイバーシティが進むとどのようなメリットがあるのかを考え、共有する場を設けたのである。
「全国の拠点で、少人数の対話型で実施したので、研修の開催は数十回にも上りました。そこでは反発もありました。事業に責任を持っている立場として、メリットが測りにくいことにどれだけ力を入れたらいいのか分からないという意見があった一方、JTIとの人財交流やグローバルな業務が多い部署ではいまさら何を言うのかという声もありました。それでも、全社で今から多様化推進に取り組むということはどういうことか、全管理職に自分ゴトとして考えてもらう必要があったのです」
こうした取り組みには、現場で仕事を覚え、現場でどのように仕事の改善が可能かを考える経験をしてきた金山氏の視点が生かされているようだ。トップダウンの一方的な押し付けではなく、現場の管理職が新しい取り組みを自分のこととして受け入れられるような場を作っていったのだ。
変化に気づかないことのリスクを回避する
日本企業の働き方の1つの形として、「阿吽(あうん)の呼吸」がある。何かを具体的に言わなくても、判断や行動の基準が伝わっていくと考えるものだ。金山氏は、阿吽の呼吸について疑問を投げかけた。

「変化のスピードが緩やかな時代ならともかく、現在の変化が早いビジネス環境では阿吽の呼吸によるコミュニケーションは本当にうまく行っているのでしょうか。阿吽の呼吸で進めてしまうと、本当は変化が起きているのに、変化に気づかないリスクがあります。きちんと言語化して、判断基準や優先順位が既存のままでいいのか、その都度考える瞬間が必要なのではないでしょうか」
金山氏は、「効率良く仕事を進める」ことの功罪も指摘する。ビジネスの多くはドラスティックに変化するものではない。変化があまりない中で、効率よく進めるために言語化して考えることをやめてしまう。その場の効率でいうと「非効率」と思えることかもしれないがあえて一息おいて考えることが、変化に対応するためには必要なのだ。
「変わっていくことをポジティブに捉えてもらうことが、まず大切です。研修では、みなさんに共通して職場でのミーティングの場の作り方を考えてもらいました。どんな雰囲気、どんなミーティングの持ち方が良いか、ポジションにかかわらず発言を引き出すにはどうしたらいいか。いろいろな意見を1つにまとめるにはどのような方法があるか――。そうしたことを管理職同士で議論してもらいました。そこで他の現場の成功体験を共有し、現場に持ち帰って少しずつでも実践して仕事の仕方を変えていってもらうことが大切なのです」
多様化の推進が、経営課題として掲げられたとしたら、急に大きな変化や変革を求められると戦々恐々とする管理職の気持ちも分かるように思う。しかし、JTの多様化推進室は、ドラスティックな変化を今すぐ求めているのではない。現場で培ってきた多様な経験を共有することで、そして「今までのJTのやり方も適用する」ことで、少しずつ変わっていくきっかけにしようとしている。それが、女性が働きやすい環境の推進につながり、グローバル時代の多様化への対応へとつながっていく第一歩なのだ。
text:Naohisa Iwamoto pic:Takeshi Maehara