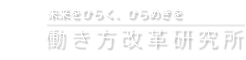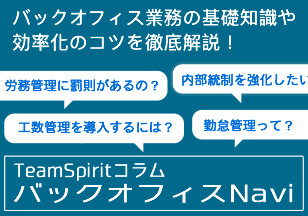一年前にプロ棋士に勝ち越した「アルファ碁」は、その後"謎のネット棋士"の「Master」として、この正月にはトッププロを含むネット碁の高段者たちを相手に破竹の60連勝を果たすという快挙を成し遂げました。アルファ碁で一躍有名になったディープラーニングを始めとする人工知能(AI)の手法は、クラウド上でも公開され、一般の利用へのハードルも一段と低くなっています。さらにこれらはビッグデータやIoT、ウエアラブルコンピュータと組み合わせることで、未来の働き方にも大きな影響を与えることになるでしょう。
「ライフログ」は働き方にも影響を与える
「ライフログ」という言葉が流行したのは数年前のことです。日頃のネットやSNSでの行動が全てデータとして記録され、そうしたデータを活用することで無限の可能性が広がるとの期待が大きく膨らんだと思います。当時はデータを記録するのに手間がかかることもあって、どちらかというと概念先行だったこの考え方が、ビッグデータやIoT、さらにはウエアラブルデバイスの発展によって大量のデータの入手が現実的となり、収集コストも激減して日常的に応用可能なものになってきました。
ライフログは日常生活全てに関わるものですが、これを「ワークログ」として捉えれば、仕事の日常にも様々な応用が考えられます。ここでのワークログというのは営業日報のように人間がわざわざ記録していくものではなく、単に行動していくだけで「勝手に」記録されていくデータのことを意味しています。
これは単にどこどこの顧客にいつ訪問したとか、どんな提案をしたとか、あるいは社内でどんなドキュメントをどこの部署に通知したのかといったやりとりのみならず、ある提案書を作るときに、どのデバイスをどこで何度開いて、一回の作業にどれだけ時間を使い、その間に誰にどんな問い合わせをしたかといった、従来であれば記録に残らなかったような情報も自動的に蓄積されていくことになります。
さらには、一見仕事と関係ないような「前の晩に何を食べた」とか、「その前の週に何の本を読んでいた」といったプライベートの内容までが商談の成否とどう相関するのかといったことまでが成功要因や失敗要因として「裏で」データ解析できるようになります。こうなれば、従来語られていた「成功(失敗)パターン」の構図が一気に塗り替えられることもあり得ます。
「新しいお客さんの商談を成立させるには土曜日に家の近所のスターバックスで資料を作るべし」といったような「マイ成功パターン」をAIが教えてくれる、なんていうことも十分にあり得るでしょう。
ここまでやるとなると、ログの収集に関してはプライバシーが問題となりますが、このようなワーク(ライフ)ログはあくまでも自分だけが利用可能な「学びの源泉」とするという条件をつけることもできますから、収集や利用のハードルも一気に下がることになると考えられます。
成功談、失敗談をワークログが補完する
このような動きは、ビジネスにおける学びの仕方にも変化をもたらすことになります。これまで重視されてきた「うまくやっている人の成功談をまねる」ことの限界も見えてきます。
このような個人の成功談や失敗談は有効であることは間違いありませんが、反面「後付け」のバイアスが相当かかっていることも否定できません。年配者の「健康の秘訣」などでもよく見られることですが、往々にして「自分が良かれと思ってやっていたこと」が唯一の成功要因として語られることがあります。
このようなことが起こるもう一つの原因として、成功(失敗)談の網羅性の欠如が挙げられます。その人や会社がやってきた全てのことが考慮されているわけではなく、「ほんの一部」の取り上げられやすいことが取り上げられてしまう傾向にあります。
こうしたバイアスから逃れるためにも、「恣意的に収集された一部のデータ」ではなく、「自動で勝手に収集された網羅的なデータ」からの判断という側面が重要になってくるのです。このようにして収集されたデータからであれば、文字通り全体の中で重要性や相関の高い行動のみならず、他者との比較に置いて「何をやったか」だけでなく「何をやらなかったか」といったことまで可視化されることになります。
このように従来の「主観的かつ恣意的」な個人の成功(失敗)談を「客観的かつ網羅的」なAIのリコメンデーションが補完することで、仕事の仕方も「意外な発見」から大きく変化していくことになるでしょう。
このような「新しい働き方」の下では、昔から繰り返されてきた「ベテランの成功体験(自慢話)を『頼りない若手』が聞かされる」という「若手育成」の構図も崩れていくことになるかもしれません。「俺たちの若いころはなあ・・・」と始まるお説教に対して、間髪入れずに「それは『昔』はお客さんとのやり取りが○○だったからですよね」とデータで反論するICTに精通した若手といった構図になったり、さらに進めばそのようなやり取りそのものが「AIコンシェルジュと人間」によって繰り広げられていったりという姿も遠い将来ではないのかもしれません。