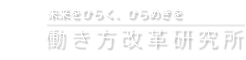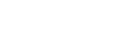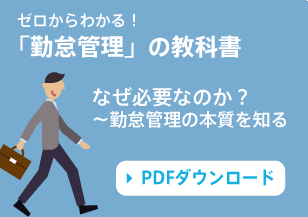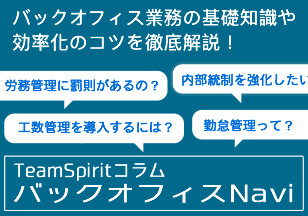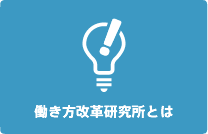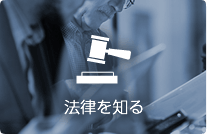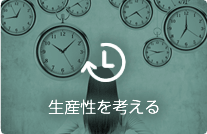今回から話題を転じて,「ナッジ」の話題を数回にわたって取り上げよう。ナッジについては2017年11月に取り上げたが,ここではナッジが,多くの国や公的機関で行なわれた公共政策手法として有効なばかりでなく,企業や組織にとっても重要な手法であることを見ていく。
ナッジとは
まずナッジとは何かについて,おさらいしておこう。この概念は,2017年のノーベル経済学賞を受賞したアメリカの行動経済学者リチャード・セイラーと,オバマ政権で大統領のブレーンを務めた行動経済学者であり法学者であるキャス・サンスティーンが共著『実践行動経済学』の中で提唱したものである。ナッジとは,もともと「軽くつつく」とか「背中を押す」といった意味で,人の行動を後押しする,行動を促進させるといった意味である。
ナッジの例
ナッジの例として,ロンドンで横断歩道の歩道側端に書いてある「右を見よ」というサインがよく取り上げられる。これは,アメリカやヨーロッパから来た,車の左側通行に慣れない旅行者に,まず「右を確認せよ」と注意を促すサインである。同様に,カフェテリアで,サラダなどの健康によい品を,利用者が取りやすいように陳列のはじめの方に置き,並んだ人が無意識でサラダを取るようにするという手法である。シカゴの学校で試したところ,健康に良い食品を取りやすく配置するだけで,健康食品を選ぶ人の割合が以前に比べて35%も増えたという。これらは身近なナッジとしてよく知られた例である。
ナッジと公共政策
ナッジ理論が注目されるようになったのは,何といっても公共政策の分野で顕著な成果を挙げられると期待できるからである。これもよく知られた例であるが,セイラーとサンスティーンは,アメリカでいかに人々に貯蓄をさせるかという問題の解決法として,ナッジを提案する。アメリカには年金制度として401(k)のような確定拠出年金制度がある。従来は加入希望者がさまざまな選択肢を検討して自分で選択する必要があった。セイラーらは,初期設定で全員に加入させ,加入を希望しない者はそうすることもできるような仕組みを提案した。その結果,加入率は49%から86%に跳ね上がったという。この「初期設定で加入」という方法がナッジなのである。
ナッジは行動経済学の一部であるが,イギリスのキャメロン政権は通称「ナッジ・ユニット」と呼ばれる行動洞察チームを立ち上げ,政府に対してナッジのような行動経済学の考え方を政策に導入するように提案している。セイラーはこのチームの立ち上げに関わっていた。アメリカでは,サンスティーンはオバマ政権時にホワイト・ハウス入りしている。その他の政府や公的機関もナッジの手法を実際に政策に組み込んだり,そのための検討・提案組織を持っている。OECD加盟国では,202もの政府や公的組織が公共政策にナッジを含む行動経済学的手法を用いているという。わが国はナッジを行動経済学を政策に活かすという点ではかなり遅れている。現在多くの省庁でそういった手法を検討・提案しているが,具体的な政策への適用例はまだほとんど見られない。
人は非合理的
ナッジが行動経済学のなかで特に注目されるようになったのは,人間は必ずしも合理的ではなく,ヒューリスティクスを用いたり,バイアスのかかった判断をしがちだということと大いに関係がある。以前から何度も取り上げたように,人の脳にはものごとを判断し,決定するための2つのシステムが備わっている。システム1は,直感的・感情的反応であり,無意識のうちに,素速く,努力することなしにものごとを判断し,結論を出す。これに対してシステム2は,理性的・熟慮的判断を行ない,意識的に行なわなければならず,時間がかかり,実行には努力やエネルギーを必要とする。
システム2は怠け者で,しばしばスイッチが入らず,入ったとしてもすぐに疲れてしまう。簡単に言えば,人は考えるのが苦手なのである。ナッジの考え方は,システム2に頼らずに,システム1をうまく用いることによって,ナッジされる人の満足を高め,それが公共の福祉や社会の安定につながるようにすることである。たとえば前述の,カフェテリアの例では,人は,料理の陳列があると,無意識のうちに初めの方にある料理を取ってしまうという性質を利用するものであり,貯蓄を殖やすナッジは,人は,初期設定を変更することは少ないという性質を利用したものである。つまりシステム1を活用するのである。
選ばない自由
注意すべきは,これらの選択肢は,考慮の末,選択しないという決断も可能であることである。強制ではないのである。ナッジされた選択肢が自分の欲するものではないと思えば,違う選択肢を選ぶことができるのが,ナッジの基本である。このような介入方法を,セイラーとサンスティーンは,「リバタリアン・パターナリズム」と呼ぶ。つまり,「やめる自由を残したお節介」なのだ。
人を動かすには
一般的に人を動かすにはいくつかの方法がある。まず,法的な規制や組織内の規則がある。「これこれをしてはいけない」あるいは「これこれをしなくてはならない」といった行動を縛る方法である。次に,説得や教育がある。「した方がいい」ことを当事者に伝え,当事者自らが行動するようにすることである。第三に経済的インセンティブを用いる方法がある。ある行動をすることで金銭的利得が得られるならば,その行動をより多くするようになるだろう。逆に,行動を抑制したい場合には,罰金を科すことでその行動を少なくすることができる。そして最後に,誘導という方法がある。ある行動をするように人を導くことである。ナッジはこの最後の方法に含まれる。
企業におけるナッジ
ところで,ナッジが有効であることが期待できるのに,あまり適用されていない分野がある。それが企業や組織における意思決定である。従業員を適切にナッジすることによって,彼らの仕事に対する満足度を上げ,成果も向上し,その結果として企業の業績も上昇すると期待できる。従業員のよい健康状態や健全な金銭管理をもたらすことも可能なのである。しかしこの方法は,十分に評価されているとは言えない。
逆に,ナッジを効果的に利用して,成果をあげている企業の代表例がグーグルである。同社の上級副社長であったラズロ・ボックの著書『ワークルールズ!』には,同社が用いて成果をあげているナッジの例がいくつも紹介されている。
次回から,グーグルの例を参考にしつつ,企業や組織にとってどんなナッジが考えられ,効果的であるかについて具体的に見ていこう。
参考文献
リチャード・セイラー,キャス・サンスティーン『実践行動経済学』(日経BP社2009)
ラズロ・ボック『ワークルールズ!』(東洋経済新報社2015)