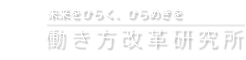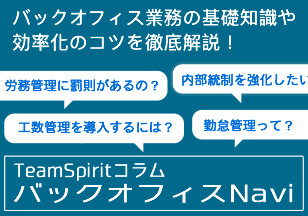昨年末に宮崎謙介衆議院議員が、育児休暇を取得する旨を宣言して物議を醸し出した。自民党内では大事な議決において票が1票減ることが危惧され反対意見も多かったが、宮崎衆議院議員は、衆議院議員が前例のない父親の育児休暇を取得することの意義と重要な時には国会に出向くという柔軟な姿勢を説明し、周囲を納得させたという報道を目にした。日本では、男性が育児参加したくても難しい現状にあることが浮き彫りになったが、シンガポールではどうだろうか?
シンガポールでは、昨年の8月から、それまで1週間だった有給の「Paternity Leave(父親の育児休暇)」が、政府主導で1週間追加され、計2週間となる方向で調整が始まっている。この追加分の1週間は、政府が給与を出し、企業は休みを与えるという方法で、休暇を取る本人にとっては有給休暇となる。父親には、子供の生後4ヵ月以内に連続2週間の休暇を取るか、1年以内に計2週間の休暇を上司と相談しながら取るかの選択肢が与えられている。現在は、公務員と大企業が中心となってボランティアでこの制度に取り組んでいるが、政府は数年以内に必須とすることを目指している。
シンガポール政府が父親の育児休暇制度に積極的な背景
シンガポール政府が父親の育児休暇を増やす背景には、少子高齢化の課題がある。シンガポールの出生率は2.0を大きく下回り、日本以上に厳しい少子化傾向にある。日本と異なり移民を積極的に受け入れることで人口は減少していない。しかし、高齢者を支えるため、そして、主に中国系、マレー系、インド系から成る主な民族の割合を維持するために、政府は出生率を上げるために育児休暇や在宅勤務を推奨している。
2015年8月のストレートタイムズ紙の記事によると、父親の40%以上が1週間の育児休暇を取得しているとのことだった。追加された1週間の取得状況については、まだデータが集まっていない状況のようで特に公表されているデータはないが、先日現地のラジオ局の番組で父親の育児休暇が2週間では足りないことを議論していたところから、2週間の育児休暇はある程度消化されていると思われる。
父親の育児休暇制度は、シンガポールでは活用されているのか?活用しやすい環境なのか?
では、シンガポール人の男性は、休暇が取りやすい環境なのか。今までシンガポール人と話をした経験から、彼らが何らかの休暇を取ること自体に積極的だとは思えない。シンガポール人の男性は40歳または50歳まで兵役の義務があり、それが昇進の足かせになっていると思っている人が少なくないからである。シンガポールでは18歳から2年間兵役の義務があり、それを終えた後は、予備役として最低でも40歳まで非常事態に備えて毎年最大40日間の訓練を受けなければならない。
最初の兵役で生じる2年間のブランクによって社会人1年目から同級生の女性に2年間遅れをとり、その後も継続的に予備役として2週間は拘束され、拘束されるタイミングも個人の仕事の事情などは加味せずに呼び出される状況に、焦らずにはいられないと訴える人が圧倒的に多い。この状況下であるため、有給だからといって育児休暇を喜び勇んで取っているとは思いづらいのである。状況は父親が育児休暇を取得するのに厳しいものであるが、やむを得ず取得していると思う。
2015年3月のストレートタイムズ紙によると、1960年代、70年代ではほとんどの母親は専業主婦だったものの、2014年の労働力人口の動向データでは25歳から54歳までの女性の76%が就労しているという。つまり、シンガポールではこの50年間のうちに女性が社会参画する権利が広く認められ、多くの家庭が共働きに変化したということである。それに伴い、父親も子育てに従事する必要が出てきたと考えられる。また、日本と異なり、欧米同様に里帰り出産の風習はない上、女性が出産時に入院するのは、出産が順調なら1日間だけであるため、夫の育児休暇の必要性は高い。
シンガポール人のイクメンぶり
ローカル小学校の個人面談を覗くと、父親参加率の高さに驚かされる。季節行事のボランティアなどは母親メインだが、個人面談や保護者会となると、父親の姿が目立つ。受験競争が激しいシンガポールでは、個人面談や保護者会は重要だという位置付けだろうが、面談のみならず、日常の子供のケアも父親が負担している場面をよく見る。担任教師とクラスの保護者で作るグループチャット(LINEではなくWhatsAppが主流)に父親が登場したり、子供たちが自宅で遊ぶ予定を立てるためにもらってきた電話番号に連絡すると相手が父親だったりと、イクメンぶりが垣間見られる。仕事の最中に、友達の家に遊びに行った子供のお迎えの時間を相手の親と携帯のチャットでやりとりしている父親の姿は、日本では想像できないと思う。
また、祝日でない日に学校が休日の場合は職場に子供を同伴し、子供を勉強させながら仕事をする姿も珍しくない。日本の学校では考えられないが、突然、学校側が1週間後に休日を設定することもあるため、これはやむを得ない。共働きが多いシンガポールでは、同僚も寛容に受け止める。これらの行動は、仕事をサボっているのではなく、致し方なく取っている行動であることを多くの人が理解している。シンガポールでは、自分の私的な事情で業務上の判断を捻じ曲げるような公私混同は許されず、背任行為に対する罰則は厳しい。一方で、家庭の事情で仕事のやりくりを工夫する公私混同については、比較的寛容だと思う。これは、多くの父親が子育て期間中の時間や段取りのやりくりの苦労を経験しているからだろう。
日本とは異なる文化――見過ごせない介護問題
シンガポールでは近い将来、育児を終えた多くの父親が、次は介護に時間を割かなければならない状況になることが想像される。出生率が日本以上に低いシンガポールは日本より先に超高齢社会になると言われているが、日本より遥かに介護環境が厳しい。まず、子が親を扶養することが法で定められている。身体的、精神的、金銭的に救済しなければならない。欧州では、老人介護は社会で担うものというコンセプトだが、シンガポールにそのコンセプトはない。法律からは、老人介護は家庭の問題であり、家庭で行うものだという明確なコンセプトが見える。それを受けてか、介護福祉施設が充実していない。金銭的にも、日本のような介護保険もない。現在要介護老人のいる多くの家庭が頼りにしている外国人の住込みヘルパーも、給与水準が年々値上がりし、雇いづらくなってきている。こういう事情があって、人口減少が起きていない中でも少子化問題の解消が急務となっている。子育てや介護と仕事が両立できる社会の実現を目指し、政府は、ホワイトカラーの生産性の向上や制度の充実、地域ボランティアの充実などに取り組んでいるが、今の子育て世代が味わっている育児と仕事の両立の苦労は、将来、介護をも調和させるライフスタイルを下支えする社会の寛容さを生み出すことに大きく寄与するだろう。
冒頭で触れた宮崎衆議院議員のケースのように、本来は父親の育児休暇制度が整っていなくても、上司や人事部、マネジメントの裁量で事実上の父親の育児休暇は実現できる。しかし、現在の日本では、周囲の人と同じスタイル、同一な雰囲気を維持しなければ周囲から受け入れてもらえない文化が主流で、チームに物理的に迷惑をかけることになる休暇の取得は妬みまで買ってしまうことがある。この文化的背景を加味すると、日本では、育児や介護に対応できる新しい働き方を可能にするために、最初に制度を整えることで敷居を低くし、前例を作っていくことが不可欠だと考える。このような努力を重ねるうちに組織文化に多様性を受け入れる寛容さが生まれてくることを期待したい。