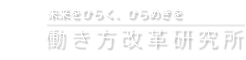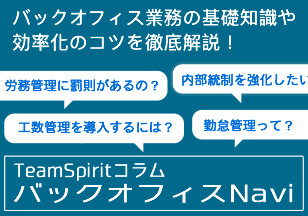前回に引き続いて、競争が不正に与える影響について見ていこう。
不正は大きく分けて2種類ある。1つは自分の利益を直接高めることである。このためには金銭や物品を盗んだり、自分の業績や成果を実際より高く申告したりする方法がある。
もう1つは、他人の成果を低くすることで、相対的に自分の利益を高めることである。他者の成果や業績を実際より低く評価・申告する方法や、悪い結果を他者の責任とする方法がある。他者の行動を妨害したり、悪評を流すことも含まれる。
競争がある時に、行動の成果を自己申告する場合と、他者の成果を申告する場合とでは、不正はどのように異なるだろうか?
競争下の不正に関する実験
この点を実験的に確かめたのが、心理学者で行動経済学者のリグドンとデステレの研究である(文献1)。彼女らは、このブログで以前説明した、ダン・アリエリーらが用いたのと同じ実験方法を使っている。すなわち、小数が12個あり、そこから「3.67と6.33」のような、足して10になるペアを見つけるという課題だ。
同様の問題が20問出され、正答1問につき50セントもらえるという条件で、実験参加者に5分間で解かせた。まず最初は、競争がない条件で実験を行ない、実験者が採点して基準とする。その後に、競争の要素はないまま、自分の成績を自己申告するという条件で実験が行なわれた。
さらに次からがこの実験の狙いであり、アリエリー実験にはなかった「競争」という条件がつけ加えられた。競争は、実験参加者をランダムに2人1組にして(相手は特定できない)、成績の良かった方だけが、正答1問につき50セントもらえるという形式である。
さらに、この条件での実験は2つに分けられた。1つは、回答用紙は破棄して、自分自身の結果を報告するものである。もう1つは、ペアを組んだ相手の成績を報告するというやり方である。
さて、この実験の結果はどうだっただろうか。競争が加わっても、自己申告の条件では、競争がない場合と比べて、参加者の不正の程度は変化しなかった。一方、相手の成績を申告する条件では、不正な申告は目に見えて減ったのである。自分のことをよく見せる不正はしても、他者を貶めてまで自己の利益を追求することはしなかったのである。
小売店で、店員たちに売上を競わせ、もっとも多かった人に報酬金を渡すというやり方がある。
上の実験から言えることは、売上を自己申告させると不正が行なわれる恐れがあるが、店員同士でペアを作り、相手の売上を申告するというシステムにした方が、不正は小さくなると期待できる。
2つの異なる競争の下で、勝者はどう"不正をする"か?
競争には2つのケースがある。
1つは、競争が社会的比較によってなされる、つまり、他者との比較で勝ち負けが決まるケースであり、もう1つは、目標や目的を達成できるかどうかで勝敗が決まる競争である。この2種類の競争は、勝者の不正に対してどのような影響を与えるのだろうか。
これを確かめたのが、イスラエルの研究者であるシュールとリトフの一連の実験である(文献2)。
まずは出発点となる、競争を伴う実験である。
コンピュータ・スクリーンに次々と小さな図形が表示され、実験参加者はその数を推測するのが課題である。参加者はランダムにペアに分けられて課題に取り組み、成績が良かった方にちょっと高級なイヤフォンが賞品として与えられると言われた。しかし実際には、勝者で賞品をもらえる者は抽選で選ばれていた。もちろん実験参加者はこのことは知らない。
次に、やはり参加者をランダムにペア分けした。今度は、サイコロ2つをテーブルに置き、その上に不透明なカップをかぶせてよく振り、出た目によって、12シェケル(イスラエルの通貨単位:約300円)のうちそれぞれの取り分が決まるというルールである。
1人はカップを振る役目であり、もう1人は見ているだけだ。サイコロの目の和(2~12)に応じて、振った人の取り分が決まり(目の和が6なら、振った人に6シェケル与えられる)、残りがもう1人の取り分となる。
面白いのは、実は、カップの底に小さな穴が開けられていて、振った人は、出た目が見えるようになっていた。そして、サイコロの目の和は、カップを振った人が自己申告するというものであった。つまり、振った者は実際よりも大きい数が出たと申告するという不正を行なうことで、自分の取り分を大きくすることができるのである。
この実験の結果が興味深い。
サイコロの目の和はランダムに決まるはずなので、全体の請求額の和を平均すると、およそ7になるはずである。
ところが、最初に行なわれた推測実験での勝者は、平均8.75という過大な請求をしたのである。敗者の方は、平均6.35であり、7より少し小さいが有意差はなかった。
つまり、最初の実験で勝者となった者は、続けて行なわれた無関係な実験で、自分に有利になるように不正な申告をしたのだ。敗者にはその傾向は見られず、競争の勝者だけがこのような不正をしたのである。この不正の被害者は実験実施者ではなく、同じ実験に参加した仲間であり、仲間の取り分を横取りしたことになる。
次の実験は、まず過去に競争で勝った経験や目標を達成したという経験を思い出してもらい、その後、上と同じサイコロ入りカップを振るという方法である。
ここでも、以前に他者との競争で勝った経験を思い出したグループは、平均8.89という過大な申告をした。目標達成を思い出したグループでは、平均7.16と理論的平均値とほぼ一致した。競争に勝ったことを思い出しただけで、不正が増えたのである。
さらに、実際にくじに当たるとか、目標を達成するという要素を盛り込んで実験が行なわれ、どちらの場合も、勝者と敗者の申告数の差はなかったことが確かめられている。
実験から導かれる経済社会における競争の"副作用"
これらの実験でわかったことは、他者との競争に勝つとその後の無関係な状況でも、不正が増えるということである。これはいったん競争に勝つと、勝者は一種の「権利」あるいは「資格」を得たという意識を持ち、それに基づいた行動をするからだと考えられる。このことは、「心理的権利尺度」を測ると、勝者の方が敗者よりかなり高い点数を獲得するということで確かめられている。
競争が社会的比較によってなされる場合、つまり、他者との比較で勝ち負けが決まるときには、不正が多くなる。一方、目標を達成する、決められた基準を満たす、幸運に恵まれるといった場合には、不正は小さい。
前者のような競争での勝者は、敗者に比べて、競争が終わった後でも、その競争とは無関係な状況においても、不正をしやすいのである。つまり、競争の勝者は将来も不正をしやすいことになる。このような勝者の態度は、単にうまくいった、成功したというよりも、競争に勝ったことが原因となっている。
競争は経済社会にさまざまなメリットをもたらすが、競争の勝者による不正の増加という予期せぬ副作用をもたらすことになる。
参考文献
(1) Rigdon,Mary L. and Alexander P.D'Esterre, 2015, "The Effects of Competition on the Nature of Cheating Behavior", Southern Economic Journal, 81(4).
(2) Schurr,Amos and Ilina Ritov, 2016, Winning a Competition Predicts Dishonest Behavior, PNAS, 113, 7, 1754-1759.