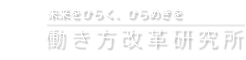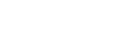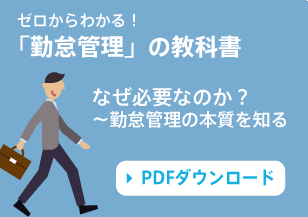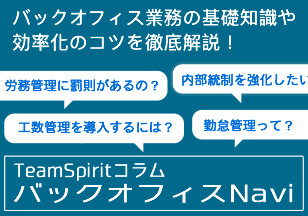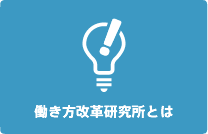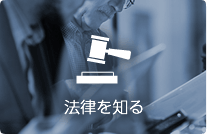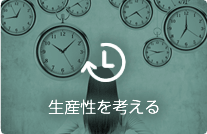2020.07.30

2019年5月に「女性活躍推進法」の一部改正が決定したことにより、改革のメスが入り始めています。今後は多くの企業が女性の雇用に関してより真剣に情報を収集し、より厳密に法律を遵守する必要性があるでしょう。時代に合わせた人材採用や女性が働きやすい環境の整備が今後は必須となってくるだけに、企業としてはどのように法対応していけば良いのでしょうか。具体的な取り組み方について解説します。
>記事を読む
2020.06.17

2020年6月から「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が施行されたことをご存知でしょうか。かつての雇用対策法ではありますが、2019年5月の改正でパワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務づけられました。「パワハラ防止法」の施行が企業や労働者にどんな影響を与えるのかについて迫ります。
>記事を読む
2020.05.26

従業員の働きやすさやワークエンゲージメントを高める施策は、企業の魅力に直結すると言っても過言ではなく、会社選びの際に福利厚生を重視する人も多いでしょう。そうした背景があるだけに、企業は従業員の生活の質や満足度の向上に着目し、福利厚生の充実をより図っていくべきだと言えます。では従業員が喜ぶ福利厚生とは、どんな内容なのでしょうか。
>記事を読む
2020.02.05

ペーパーレス化を推進する改正方針で、2020年以降はバックオフィス業務にかつてないほどスポットライトが当てられるかもしれません。「バックオフィス業務は社内でずっと書類対応に追われている」というイメージから、どのように変わっていくのでしょうか。
>記事を読む
2019.10.07

法改正によって企業は時間外労働の見直しを本気で取り組む必要がありますが、そうした変化の流れにすべての企業が対応できているかと問われれば、決してそうではありません。では未だに「時間外労働の上限規制」への対応に着手できていない企業の場合、どんなことに注視して対応を急ぐべきなのでしょうか。今回は大企業での運用の取り組みを参考に、今後の対応策について検証します。
>記事を読む
2019.07.23

高度プロフェッショナル制度の対象業務は「高度の専門知識等を必要とし、その性質上従事した時間として従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして、厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」とされています。
>記事を読む
2019.07.23

「勤務間インターバル」とは、終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間(インターバル)を設ける制度です。
日本ではまだ導入事例が少ない制度ですが、EUでは加盟国の最低労働基準を定める「労働時間指令」において、勤務間インターバル制度を設けることが義務づけられています。今回は勤務間インターバルに関して紹介します。
>記事を読む
2019.06.17

皆さんは「36(サブロク)協定って何?」と聞かれたら、正しく答えられますか?36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。会社が法定労働時間以上の残業や法定休日出勤を従業員に課す場合には、本来は労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています。
>記事を読む
2019.02.06

2018年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、2019年4月1日から順次、雇用対策法、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法、パートタイム労働法、労働契約法、労働派遣法など多岐に渡る法律が改正されます。法施行まで残り3か月を切った今、各企業が何を準備すればいいのか、法律がどのように変わるのかを踏まえ、3回に分けて説明します。
>記事を読む
2018.12.10

2019年4月から「改正労基法」が施行されることで、多くの面で働き方が変わることになる。それに合わせた労務管理の対応も必須だ。その中で、最も注目されるのが「年次有給休暇の年5日取得を義務付け」だろう。これを遵守し円滑に実践するためにも、勤怠管理の情報は重要だ。その理由等について考察する。
>記事を読む